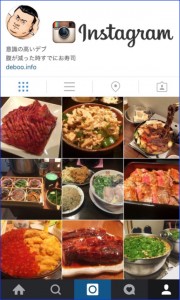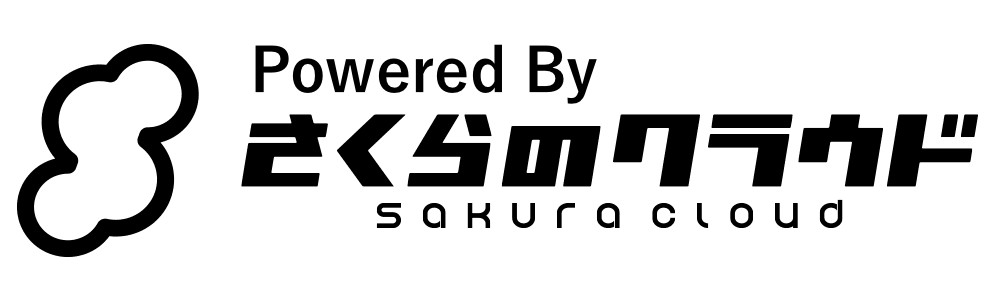もし、村上春樹風に「意識をこじらせたデブとメンヘラ気味な彼女」の一日を書いたら
「あなたは何が好きなの」と彼女は訊ねた。
「背脂」と僕は言った。
「違うの。私が聞きたかったのは何の音楽が好きかということ」
「悪いけどさ」と僕は続けた。
「食事の席で音楽の話しはやめてもらえないかな。」
彼女はひどく動揺していた。まるでセルゲイ・ラフマニノフのような深刻な顔をした彼女を見て、僕はなんだかとても悪いことをしてしまったような気がした。
※
彼女とは—–大学の吹奏楽サークルで知り合い、仲良くなった。
当時僕は大学一年生で、彼女もやはり一年生で、先月まで学食で品の良い豚骨ラーメンを出す女子校に通っていたお嬢さんだった。
腹太鼓しかできなかった僕に、親身になって楽器を教えてくれたのは彼女だった。シタールというインドの弦楽器で、彼女は何十分もかけてシタールの素晴らしさについて語ってくれた。
「調律のやりかたはわかるかしら。」
僕は少しおどろいた。それまで腹太鼓しか知らなかった僕は、楽器なんてものは取り出せばすぐに演奏できると思っていたからだ。
「その様子じゃ知らないようね。私が教えてあげるわ」
どうやら彼女は僕に調律のやりかたを教えたがっているようだった。僕は彼女から手ほどきを受けながら調律を試みた。
「違うの、そうじゃない。糸巻きはもっと注意深く取り外さないと」
「ブヒ?」
「駄目よそんなに削りすぎちゃ。そこは軽くやすりをかけるの。わかる?」
「ブヒッ?」
僕は出来る限りを理解しようとしたが、正直いって自信が持てなかった。お腹が空いていたからだ。
「あなたって本当に不器用なのね。まるで人間の動きを真似ている豚そっくりよ」
「ブヒッ?」
女は顔をしかめ、深く息をつき、何も言わずシタールをケースに戻した。グラスファイバー製の頑丈なケースだった。それから彼女は鼻梁に手をやり、まるで棒を投げても取りにいかない犬を見るような目で僕を見た。すごく賢明で妥当な判断だと僕は思った。
「僕は空腹であるとなにも頭には入らないんだ。」僕はそう言った。僕はだいたいにおいて冬眠前の熊のようによく食べるのだ。
「君は平気そうだけどお腹が減ってないのかい?」と僕は訊ねた。
「空いてるわ。でも私は平気。そんなことでどうもなったりはしないわ。」と彼女は言った。
「それは凄い才能だよ。一体どうやったら—–」
「あら、こんなの簡単よ。才能でもなんでもないのよ。要するにね、今は満腹であると思いこむんじゃなくて、空腹であることを忘れればいいのよ。それだけ」
「まるで禅だね」僕はそれで彼女が気に入った。彼女も僕を気に入ってるようだった。
「ねえ、これから食事でもいかない?」彼女は微笑みながら言った。それは本当に素敵な笑顔だった。そのへんにある何もかもをお盆に載せてもっていきたくなるような笑顔だった。
「それはありがたいな。なにしろ朝からカツ丼しか食べてないんだ」
※
四十前後の身なりの良い男がやってきて、我々のテーブルに料理を並べてきた。彼女は目の前に並べられていく料理を静かに見ていた。
「あなたは結局なに一つ楽器は向いていなかったわね。」彼女は甘えるような視線を向けながらそう言った。さきほどまでの深刻な顔がまるで嘘みたいな透き通った目をしていた。
「そんなことはないさ。腹太鼓だけじゃない。ほら。こうやって舌鼓も打てるようになったんだ。」
彼女は目も合わせてくれなかった。正確には最初に五分の一秒くらいちらっと見たが、僕の存在はそれっきり忘れられた。まるで玄関マットを見るときのような目付きだった。
「やれやれ。」僕はそう思った。彼女の感情の起伏に僕の頭は痛みはじめた。もうどうでもいいやという気分だった。
それから我々は向かいあって、口もきかずに料理を口にはこんだ。料理そのものは質素だったし、調味料の味も僕のこれまで味わったことのないものばかりだったが、決してまずくはなかった。
料理を食べ終わると熱いスープが出た。豚の骨から出汁を取ったスープだった。僕はたまらず麺を注文した。
運ばれてきた麺は細麺でスープとよく合い、僕は夢中になって食べ続けた。気がつけば頭の痛さも忘れ、何十杯もおかわりしていた。替え玉というらしい。いつしか彼女はじっと僕を見つめ、食べる様子を見守っていた。
「あなたのその食欲は、いずれ世界を飢餓に導きそうね。」
彼女はさらに続けて言った。
「その食欲を抑える方法が私にわかっていれば、すぐにでもあなたを救ってあげることができるかしら」
「あるいは」僕はわずかに残った豚骨スープを啜りながら言った。
「僕と世界をね」